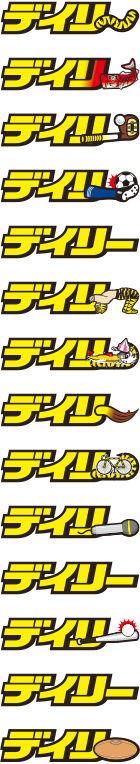もっと「歌謡曲」を大切にしよう!
10月末、デビュー50周年を迎えた歌手・大月みやこの記念コンサートを聴く機会があった。ソプラノに独特のビブラートのかかった声は健在で、いわゆる“女の情念”を歌った曲の数々にぞくぞくし、「ああ、これこそ歌謡曲」と思ったものだ。音楽界の簡単なくくりでいくと、大月は“演歌歌手”となるらしいが、私はまったく違う。ジャズ、シャンソンにも造詣が深く、ライブでも真っ赤なドレスでシャンソンを歌いあげる大月の姿は英語ではシンガーであり、日本では単純に歌手だと思う。
歌にもまして感動したのは、大月がライブ中に3度も「大先輩が歌って来た歌謡曲の名曲を私たちが継承していかなければいけない」と呼びかけたことだ。大月は18歳でデビューした時から、舞台ソデで故三橋美智也さんらの生の歌声に接して来た。「歌謡曲」と称されてきた“日本の歌”の素晴らしさを熟知しており、今や日本に「歌謡曲」の歌手などいない状況を危ぐしているのだ。
私は「歌謡曲」は洋楽のよさを採り入れ、時には邦楽までミックスさせた日本独特の流行歌だと解している。大月の持つ危機感はよく分かる。“演歌”は、「歌謡曲」の一部であり、曲調などで「艶歌」「怨歌」とも表現されるが、今や若手の氷川きよし、水森かおりにさえ、“演歌”の冠がついてしまった。J‐POPと表現が変わっていても、大衆へ支持を求める歌は「歌謡曲」であり、決して“演歌”ではないと思うが…。
昭和の日本の「歌謡曲」は素晴らしかったと思う。1960年代にGSブームの頂点に立った「ザ・タイガース」は、作詞・作曲スタッフに橋本淳、なかにし礼、すぎやまこういちら日本のトップクラスを配していた。渚ゆう子がヒットさせた「京都の恋」「京都慕情」、日活スターの山内賢と和泉雅子がデュエットした「二人の銀座」の作曲はエレキブームの中心にいた米国のバンド、ザ・ベンチャーズだった。故尾崎紀世彦さんの代表曲「また逢う日まで」は故阿久悠さんと筒美京平のコンビで「歌謡曲」にポップスという概念を持ち込んだ名曲だった。西郷輝彦を「真夏のあらし」で復活させたのは、川口真のビートを前面に押し出したロックテーストあふれる曲だった。要は日本の歌謡曲は“演歌”などという狭い枠にとらわれず、冒険をいとわない精神で大衆の支持を求めて続けて来た日本音楽界の証であり、努力の結晶なのである。先日亡くなった島倉千代子さんの代表曲「人生いろいろ」が“演歌”に聞こえたら、それはとても残念としかいいようがない。
その一方で、60年代後半から自分で歌を作って自分で歌うシンガー・ソングライターが出現し、「歌謡曲」とは一線を画した“フォーク”や“ニュー・ミュージック”と呼ばれるジャンルが生まれたのも事実だ。吉田拓郎、井上陽水、荒井由実(現松任谷)、中島みゆきらの登場によってレコードセールスが、歌謡曲を上回る状況が現出し、なにやら「歌謡曲」という言葉が古くさい物の代表格のように言われるようになった。それもイメージの問題で「歌謡曲」はきちんと“共存共栄”していた。阿久さんと都倉俊一のコンビが作り上げた“怪物デュオ”「ピンク・レディー」、宇崎竜童と夫人の阿木燿子が伝説にした「山口百恵」。百恵ちゃんと桜田淳子、森昌子の“花の中三トリオ”、郷ひろみ、西城秀樹、野口五郎の“新御三家”、松田聖子から続々と登場したアイドル群。そう、南沙織、天地真理、小柳ルミ子の「新三人娘」も忘れてはならないだろう。90年代の初頭にかけて、シンガー・ソングライターが「歌謡曲」の作詞・作曲も担当するようになり、ジャンル分けがさらに難しくなって行き、その中から「J‐POP」という言葉が流布していく。簡単にいえば「日本のポップス」の短縮形なのだが、これこそ、戦後から使われてきた「歌謡曲」そのものの表現だ。バンドブーム、打ち込み系の音、CDから配信系への転換などで、どうも「歌謡曲」と表現するのは具合がよくないとの意図から横文字を使った「J‐POP」に転換したのだろうが、その精神は変わっていない。しつこく繰り返すが、「歌謡曲」は“演歌”と同義語では決してない。
「元祖三人娘」と呼ばれた故美空ひばりさん、故江利チエミさん、雪村いずみをだれも演歌歌手とは言わないだろう。いろんな意見はあるだろうが、私はサザン=桑田佳祐を「歌謡曲の天才」だと思っている。それほど「歌謡曲」という言葉には、日本の音楽の伝統がこめられていると思う。今、「歌謡曲」という言葉を使っているのは、主なところではラジオ文化放送の深夜番組「走れ歌謡曲」、NHK総合の「歌謡コンサート」ぐらいだろう。まさに「歌謡曲」という言葉は絶滅の危機にある。だからこそ、大月がステージで訴えた「歌謡曲」への思いを支持したい。まずは、「歌謡曲」=「演歌」という誤解を解いてほしい。桑田が歌おうが、氷川が歌おうが、AKBが歌おうが「歌謡曲」は「歌謡曲」だ。その大月も67歳。先日の島倉さんの葬儀・告別式でも「ずっと後を追ってきた」と偉大なる先輩の業績に涙していた。大月の呼びかけに応えて、日本音楽界の貴重な文化財産である「歌謡曲」をもっと大切にしようではないか。
(デイリースポーツ・木村浩治)
これも読みたい
あとで読みたい
編集者のオススメ記事
コラム最新ニュース
もっとみる【スポーツ】女子マラソン・佐藤早也伽が世界選手権切符を勝ち取れたわけ 24年大阪国際の屈辱胸に励んだ驚くべき練習量

【野球】阪神最後のドラフト外選手がGMとして新たな船出 若虎時代は「相当悪ガキでした」 NPBで13年の星野おさむ氏

【野球】3・11楽天・三木監督発言の真意と選手の変化とは? 「このまま進めて開幕を迎えていいのか」厳しい下馬評覆す戦いへ

【野球】谷佳知&亮子夫妻の息子2人がアイスホッケーから野球に転向した理由 コロナが分岐点 目標はプロ野球選手

【野球】ヤクルト最大懸案事項である駒不足の先発問題の現状とは? 「4枚足りない」と高津監督も危機感あらわ 8人でローテを回す想定

【芸能】レオス・カラックス、最新作「イッツ・ノット・ミー」を語る「私自身がものすごくカオス。この映画はカオスがそのまま生きて描かれている」

【サッカー】なぜ起きた?J1広島新外国人の出場違反問題 クラブに落ち度もAFC対応疑問

【野球】ロッテ「初球ストライク率アップ」の狙い 新テーマ課した理由を建山投手コーチが語る