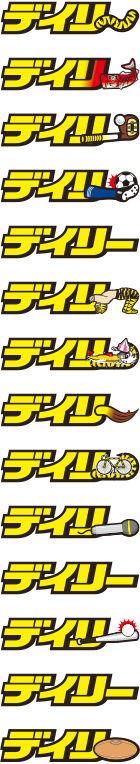【スポーツ】技術向上や審美性を追求するあまり女性アスリートが陥る摂食障害 効率的な栄養摂取は 心理面の影響も
パリ五輪は7月24日から競技が始まる。華やかなスポーツの祭典に世界が沸く一方で、特に女子アスリートの中には技術向上や審美性を追求するあまり、過度なやせ志向や摂食障害に陥る例がしばしば見られる。競技者の健康維持と食事について、立命館大スポーツ健康科学部の海老久美子教授(61)に聞いた。
女子選手の五輪参加は第2回パリ大会の1900年からスタートし、さまざまな名選手を生み出してきた。柔道やボクシングなど減量が必要な競技や、体重が軽い方が有利とされる競技もある。女子選手の中には過度な食事制限で貧血や骨粗しょう症を引き起こしたり、心理的影響で摂食障害に陥ったりしたケースも発生している。
文部科学省が19年に公表した日本スポーツ協会の「女性スポーツ促進に向けたスポーツ指導者ハンドブック」によると、「摂食障害の頻度は一般女性で5~9%に対し、競技者では18~20%と高い」とされている。海老教授は、これまで栄養指導で関わった選手の例として「『お菓子を食べると自分に負けてしまう』というストイックさを持つ選手がいたし、体重が軽い方が有利とされる競技もある。体操や新体操など審美系競技や団体競技は、体格の画一性というプレッシャーを抱くケースもあった」と話す。「身長は1ミリでもほしいが、体重は1グラムもいらない」と話す選手もいたという。
海老教授が関わっている、幼いころから新体操に打ち込んでいた元選手は10代後半、体重管理に悩んだと明かし「選手それぞれの身長に合わせた目標体重が設定され、1日に何度も体重計に乗った。体重によって選手選考が決まることもあり、計量が目的のようになっていた」と振り返った。食事も「ご飯は(質量が)重いので、食べた分だけ体重が増える。水分を含んだ食事を控え、お菓子で空腹を満たした」という。練習を終えた帰宅後すぐに食べられることもあり、菓子類に手が伸びたのだと説明する。
海老教授は「お菓子は脂肪になりやすい。エネルギーはご飯から取るのが理想。良質な炭水化物で、他の食材と組み合わせやすい」と指摘。「摂取カロリーが不足すると、タンパク質がエネルギー源に変換され、本来、体を作る栄養素が消費されてしまう」と過度なダイエットに警鐘を鳴らす。
摂食障害の予防には指導者の理解が不可欠だが、少しずつ風潮の変化もある。イギリス体操協会は昨年11月、指導者がむやみに選手の体重を測定することを禁じる規則を出した。スポーツ庁も「女性アスリートの育成・支援プロジェクト」を実施。医・科学と連携した活用した競技者、指導者の支援プログラムを行っている。海老教授は「例えば採点競技の基準に健やかさを加えるなどの幅があってもよいのでは」と話している。
効率的な栄養摂取については「暑い時期は衛生面から、出先のコンビニエンスストアで調達するのも一つの手。買う際は原材料と栄養表示を見てほしい」と話す。原材料は多く含まれるものから順に表記されている。栄養表示もタンパク質、脂質などが細かく示されており「自分に必要な栄養素を組み合わせる習慣をつけて」と、考えて食べることを勧めている。
さらに「食べられない」という心理状況になった時は、心療内科などの診察を受ける必要性を強調した上で「水分摂取だけでもしてもらいたい。お茶などの香り成分は心理的効用がある。スープなどの栄養補給を考えて」と話している。(デイリースポーツ・中野裕美子)
◆海老久美子(えび・くみこ)1962年8月9日生まれ、61歳。神奈川県出身。管理栄養士。博士(栄養学)。公認スポーツ栄養士。立命館大スポーツ健康科学部教授。全日本野球協会評議員、日本高野連理事、日本スポーツ栄養学会監事。著書に「野球食」「女子部活食」(いずれもベースボール・マガジン社)など。