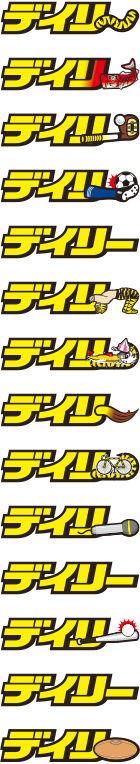中国4000年より深い!?「ソバ」9000年の歴史
蕎麦(ソバ)の原産地は中国南西部からヒマラヤ辺りで、日本でソバの栽培が始まったのは縄文時代だそうです。日本では9000年以上昔の遺跡からソバの花粉が見つかり、そのころからソバが栽培されていたようです。「蕎麦」という言葉が歴史上初めて記載されているのは平安時代の文献です。
江戸時代の中期まで「そば」は麺ではなく、「そばがき」として、そば粉を練って団子状にした、茹でた粘土のような形で食されていました。「そばきり」の名で、麺として蕎麦が食べられるようになったのは、まだ500年たらずのこと。
古くは縄文時代から食べられてきたとされているソバ。なんとなくヘルシーなイメージがありますが、実は疲労回復や二日酔い予防など、私たちをパワフルにサポートしてくれる心強い食材です。不足すると疲労や体力低下に食欲不振やイライラを招いてしまうビタミンB群。代謝を促進し、食べたものをエネルギーに変える手助けとなるパントテン酸は疲労回復にも貢献してくれます。
パントテン酸やナイアシンなどの成分は二日酔いにもってこいですし、ビタミンの一種であるコリンは、脂肪肝や動脈硬化を予防する効果もあります。さらに消化酵素であるアミラーゼやリパーゼも含まれています。ポリフェノールの一種であるルチンは、毛細血管を強化し、血圧や血糖値を下げ、膵臓(すいぞう)を活性化してくれます。
他にもソバには便秘解消に効果的な食物繊維、ウイルスに強いカテキン、豊富なミネラルも含みます。動脈硬化や糖尿病、脳梗塞など、生活習慣病の予防に優れた力を発揮してくれる食べ物なのです。どうやらこれからは「シメのラーメン」はやめて「シメのソバ」に替えたほうがよさそうですね。
◆松本 浩彦 芦屋市・松本クリニック院長。内科・外科をはじめ「ホーム・ドクター」家庭の総合医を実践している。同志社大学客員教授、日本臍帯プラセンタ学会会長。
編集者のオススメ記事
ドクター備忘録最新ニュース
もっとみる感染性胃腸炎の患者春になっても収まらない!ノロウイルスに感染しないための予防法を医師が伝授、入浴前にお尻洗って

ドクター備忘録/「はちみつ大根」の効能を医師が解説 薬膳の理論に基づいたレシピで喉を潤し脾胃を補う

認知症予防にミソ汁を アルツハイマー病は50代以降3段階で進行→年齢に適した具材を選んで

薄毛が最近気になる 男性型脱毛症に驚きの効果もたらすAGA治療薬とは 早期発見、早期治療がカギ

なぜ薬不足なのか 厚労省、財務省の施策に行き着く→「ジェネリック医薬品を普及させる」

サウナで「ととのう」ためのコツ 水分を補給し髪と体を洗いましょう、汗が出やすくなる!

5年生存率2~6%の原発不明がん 痛み、違和感で受診必要なケースは?医師が解説 原発巣は肺、膵臓など多数

10代アイドル襲ったベーチェット病 若い世代で発症、口や外陰部になどに症状、治療は難渋